百人一首の先頭歌として有名なこの和歌。でも、なぜこの歌が百人一首の先頭歌になったのかについては知らない人が多いと思います。また、この歌は天智天皇の歌と伝えられていますが、本当は天智天皇の歌ではないと考えられています。
この記事を読んでわかること
- 歌の基本事項(読み方や現代語訳など)
- 作者の天智天皇について
- この歌の魅力
- なぜこの歌が先頭歌になったのか
- この歌が天智天皇の歌ではない理由
- この和歌のもう一つの解釈
この記事を読めば、「秋の田の…」の歌についてより詳しくなれるでしょう。後半には、一般的な解釈とは違う、まったく新しい解釈もつけています。それではいきましょう。
百人一首一番歌
秋の田の 仮庵の庵の 苫を荒み 我が衣手は 露に濡れつつ
読み方
あきのたの かりほのいおの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ
現代語訳
秋の田んぼの中に建っている仮小屋の屋根の苫の目が荒いので雨漏りがする。私の袖はその水滴に濡れている。
語句解説
| 仮庵の庵 | 仮小屋。昔は秋になると田んぼに仮小屋をたてて、動物が田んぼを荒らすのを見張った。「仮庵(かりほ)」「庵(いほ)」は同じ語を並べてリズム感を出している。 |
| 苫を荒み | 苫とはカヤなどを荒く編んで作ったむしろのこと。「~を○○み」で「~が○○なので」の意味となり、ここでは「むしろ(の網目)が荒いので」の意味になる。 |
| 衣手 | 袖 |
| 露に濡れつつ | 露は水滴。「~つつ」で「~している」の意味になり、ここでは「水滴に濡れている」となる。 |
この歌の魅力
「の」の連続でリズムがよい
「秋の田の仮庵の庵の」と「の」を連続して用いることでリズムが出ています。また、「仮庵」「庵」と同じ言葉を重ねることで、こちらもリズムを整える働きをしています。
だんだんズームインしていくような情景描写
広い視野からだんだんズームインしていくような面白さのある歌です。「秋の田の」と始まることで、広い田んぼを聞き手にイメージさせます。その中にある粗末な小屋に目が留まる。さらにズームすると屋根のむしろの目が荒いことに目が行きます。そして最後は小屋の中に目を移すと、その中で男性が袖を濡らしながら静かに座っている。そんな視点の動きが楽しめる歌と言えるでしょう。
物悲しい余韻が残る
雨の降る肌寒い秋の情景。その中に濡れながら静かに時を過ごす男。こんな情景が目に浮かびます。「露に濡れつつ」といわゆるつつ止めになっているのも、物悲しい余韻を残すのに一役かっています。飛鳥時代の歌でありながら、鎌倉初期に好まれた「幽玄」をみごとに表した歌です。
天智天皇について
天智天皇(626年? – 672年)は、日本の第38代天皇であり、飛鳥時代の重要な政治改革を進めたことで知られています。彼は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)としても有名で、大化の改新(たいかのかいしん)を主導し、日本の律令制度の基礎を築いた人物です。
即位前の功績
天智天皇は、舒明天皇(じょめいてんのう)と皇極天皇(こうぎょくてんのう)の間に生まれました。彼が歴史の表舞台に立ったのは、645年の「乙巳の変(いっしのへん)」です。これは、当時の権力者であった蘇我入鹿(そがのいるか)を暗殺し、蘇我氏の専横を終わらせた政変でした。これにより、天皇を中心とした中央集権国家を目指す「大化の改新」が始まりました。
その後、彼は皇太子として実権を握り、中国・唐(とう)の制度を取り入れながら、行政・税制・軍事などの改革を進めました。
天皇としての政治
668年に正式に天皇に即位し、近江大津宮(おうみのおおつのみや)(現在の滋賀県大津市)を都としました。この遷都は、より安定した政治基盤を築くためのものでした。彼の治世では以下のような重要な改革が行われました。
- 戸籍制度の整備
民衆を正確に把握するため、「庚午年籍(こうごねんじゃく)」という戸籍を作成しました。これは日本初の全国的な戸籍とされ、後の律令制の基盤となりました。 - 軍事・防衛政策の強化
白村江の戦い(はくすきのえのたたかい、663年)で日本は唐・新羅の連合軍に敗北し、朝鮮半島から撤退しました。この敗戦を受け、日本列島の防衛を強化するために、九州の防衛拠点「大宰府(だざいふ)」を強化し、対馬(つしま)や壱岐(いき)に防人(さきもり)を配置しました。 - 法制度の整備
中国の律令制度を参考にしながら、日本独自の法体系を整えました。彼の治世の間に「近江令(おうみりょう)」が制定されたとされていますが、その内容はほとんど伝わっていません。
天智天皇の晩年と後継問題
天智天皇は672年に崩御しましたが、後継問題が原因で日本史上最大級の内乱「壬申の乱(じんしんのらん)」が起こりました。天智天皇は皇位を息子の大友皇子(おおとものおうじ)に継がせようとしましたが、弟の大海人皇子(おおあまのおうじ、後の天武天皇)が対抗し、最終的に大友皇子は敗れて自害しました。この戦いにより、天武天皇が即位し、天智天皇の政策とは異なる新たな国家体制が築かれることになります。
天智天皇は、日本の政治制度の発展に大きく貢献した天皇であり、大化の改新や戸籍制度の整備、国防強化など、後の律令国家の礎を築きました。しかし、彼の死後に後継問題がこじれ、壬申の乱という大きな内乱が発生しました。彼の政策は後の天武天皇の時代にも影響を与え、日本の歴史において非常に重要な人物の一人といえます。
なぜ天智天皇の歌が百人一首の先頭になったのか
ではなぜ、天智天皇の歌が百人一首の一番歌に選ばれたのでしょうか。それには大きく分けて2つの理由が考えられます。
最初に天皇の歌をおくことで、百人一首の格式を高められる
最初に天皇の歌を置くことで、歌集の格式を高める狙いがあったと考えられます。『万葉集』でも雄略天皇の歌が一番最初に来ています。
百人一首の編者・藤原定家(ふじわらのさだいえ)は、歌人としての名声だけでなく、歌を詠んだ人物の格式や歴史的重要性も考慮して選定しました。
そのため、百人一首の最初を飾るにふさわしい人物として、天皇が選ばれたと考えられます。
実際、百人一首の中には多くの天皇や皇族の歌が含まれており、当時の貴族社会において天皇の地位は特別なものとされていました。最初の歌を天皇のものとすることで、和歌集の格式を高める意図があったと考えられます。
天智天皇は古代の聖帝のイメージがあった
ではなぜほかの天皇ではなく天智天皇が選ばれたのでしょうか。百人一首の編者である藤原定家から見て、天智天皇は500年も前の人物です。
今から500年前というと戦国時代で、織田信長などが活躍していた時代です。相当に昔ですよね。ほかの天皇もいたでしょうに、どうしてそんな昔の人の歌を載せたのでしょうか。
それは、天智天皇に「古代の聖帝」のイメージがあったからだと考えられています。
天智天皇についての説明で述べたように、天智天皇には以下のような功績があります。
- 大化の改新
- 律令制の確立
- 戸籍制度の整備
こういった功績から、藤原定家の時代でも「昔のすごい人」というイメージがあったのでしょう。また、定家の時代の天皇の血筋をさかのぼると天智天皇に行き当たり、「今の皇室の祖」というイメージもあったと考えられます。
本当は天智天皇の歌ではない
天智天皇の歌として伝わっているこの歌ですが、本当は天智天皇の歌ではないと考えられています。
本当に天皇が本当に田んぼの仮小屋に泊まったのか
まず、日本で一番偉い天皇が、秋の雨の降る小屋に泊まって動物の番をしているという点に疑問が浮かびます。
実際には、天皇が秋の仮小屋に泊まることはなかったと考えられており、この歌も、泊まり込みで農作業をする農民を思いやる優しい天皇の歌と解釈すべきでしょう。
この歌には元になる歌があった
「秋の田の…」の歌には元ネタがありました。以下の歌です。
秋田刈る 仮庵を作り 我がおれば 衣手寒く 露ぞ置きにける
(稲刈りをする秋の田んぼで仮小屋を作って私がいると、袖に冷たい雫がついている)
『万葉集』に読み人しらず(作者がわからない歌)として掲載されているもので、この歌をアレンジしたのが「秋の田の…」の歌だと言われています。
『万葉集』にはほかにも
秋田刈る 仮庵を作り 我が置ける 苫の隙より もる月の影
(稲刈りをする秋の田んぼで、仮小屋を作って私がいると、屋根のむしろの網目の間から月の光が漏れている)
という歌が掲載されており、どうやら「秋田刈る 仮庵を作り(稲刈りをする秋の田んぼで、仮小屋を作って)」という表現は、秋の歌の冒頭としてかなり定番だったと考えられます。
一番歌ともとの歌との違い
では、元ネタと一番歌の違いはどんな点にあるのでしょうか。
秋田刈る 仮庵を作り 我がおれば 衣手寒く 露ぞ置きにける
秋の田の 仮庵の庵の 苫を荒み 我が衣手は 露にぬれつつ
同じような情景を詠んだ歌でもずいぶん印象が違いますよね。大きな違いを解説していきます。
百人一首の一番歌の方がリズミカル
まず冒頭、「秋の田の仮庵の庵の苫を荒み…」の方が「の」の連続があってリズミカルです。また「仮庵の庵」と同じ言葉を重ねることによってこちらも韻を踏んでいて心地よい感じがします。
『万葉集』の編纂された時代にはまだリズムや同じ言葉を重ねるなどの技法が確立されていませんでした。時代を下るにつれ、洗練されていったと考えられます。
「我がおれば」「寒く」が省略されている
元ネタと一番歌を比較すると、「我がおれば」「寒く」が省略されているのがわかります。「我がおれば」「寒く」は不要だと考えられたのでしょう。屋根から滴る雫で袖が露に濡れているということは、小屋の中にいるということは言わなくてもわかるよね、秋の雨の日に仮小屋にいたら寒いのなんて言わなくてもわかるよね、ということです。
言わなくてもいいことはとことん省くのが平安後期から鎌倉時代初期の流れで、その分余った字数を掛詞や枕詞など技巧にあてるのが当時の流行と言えそうです。
歌だけ見ると、まったく違った解釈も可能
この歌を天智天皇の歌として見ると、まったく違った解釈も可能になります。「仮庵の庵」をはかない天皇の立場と見る説です。飛鳥時代というと、権力というのは政治的な理由で奪われてしまう可能性があった時代。特に天智天皇は乙巳の変で蘇我氏から権力を奪った張本人です。周りにはまだまだ蘇我氏寄りの人も多かったはず。そんな中で、天皇の立場のはかなさを詠んだ歌とも解釈できるのです。
| 秋の田の仮庵の庵 | いつ壊されてしまうかわからない、自分のはかない天皇という立場 |
| 苫を荒み | むしろの網目が荒いように、自分の権力にはまだ隙があり、盤石ではない |
| 我が衣手は露にぬれつつ | 自分の地位のはかなさを思うと涙が止まらず、その涙で袖はぬれっぱなしだ |
「仮庵の庵」を自分のはかない立場ととらえると、歌の意味は以下のようになります。
秋の田んぼの仮小屋のようにはかないこの天皇という立場。屋根のむしろの目が荒いように、私の権力も盤石ではない。それを思うと涙が止まらず、私の袖は常に濡れている。
袖が濡れるという表現は、遠まわしに泣いているという意味に使われることがよくあったので、この解釈も不自然ではありません。もし天智天皇が不遇な最後を遂げた天皇であったなら、この解釈も説得性を持つでしょう。
この解釈はおそらく後付けで「こういう風にも読める」というだけに過ぎませんが、和歌の多様性を考える上で面白い解釈と言えます。
百人一首をもっと楽しもう
百人一首は鎌倉時代の天才藤原定家がこれぞという和歌を選りすぐったベストアルバムのような作品です。知れば知るほど深い面白さを体感できるでしょう。100首しかないので、ほかの歌集などと比べて読みやすいのもポイントです。ぜひ和歌の世界の奥深さを楽しんでください。
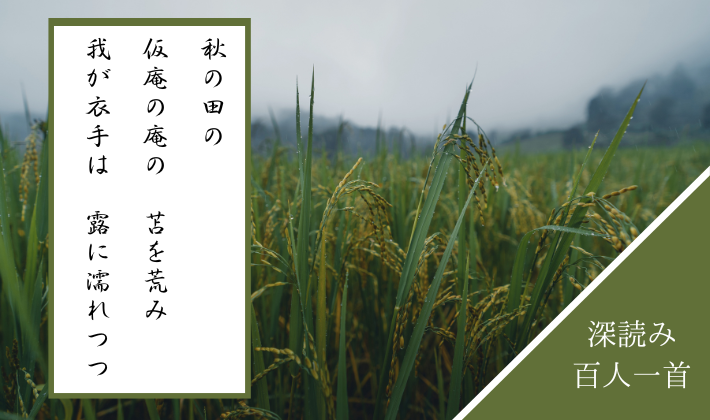

コメント